データドリブンな顧客マーケティングにおけるセグマップと顧客KPIツリーの役割と連携|3.セグマップと顧客KPIツリーの関連と適切な利用方法セグメント
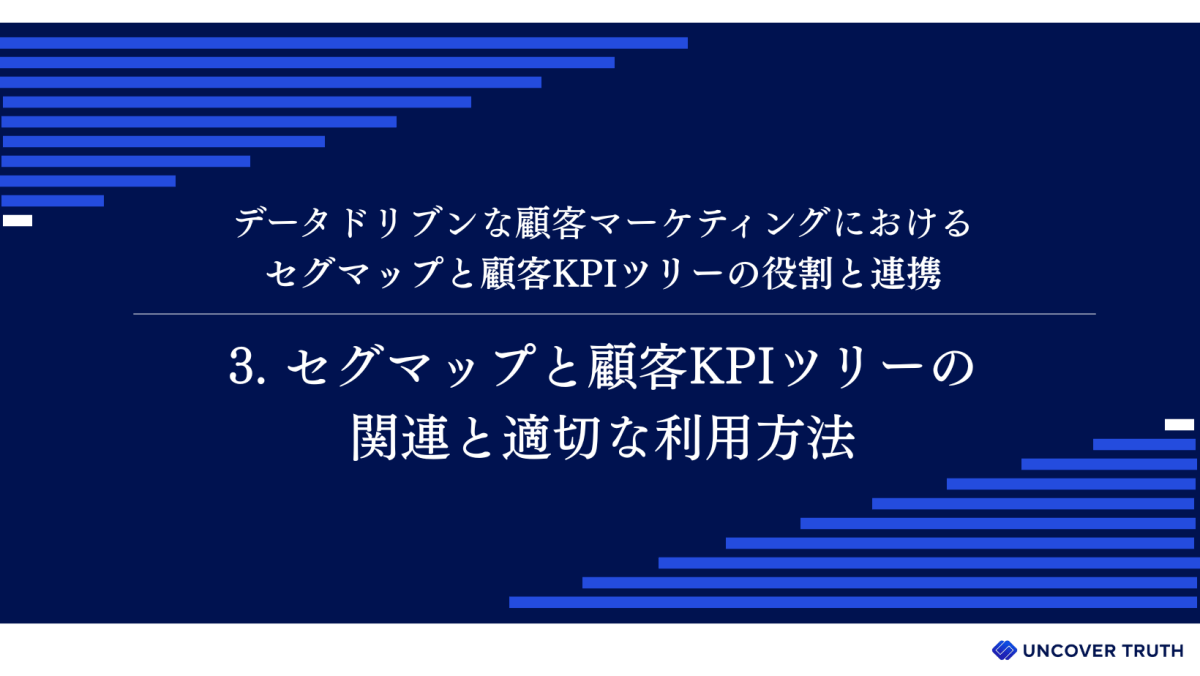
ステージに応じてどのようにデータ活用を進めていくべきかを考える際、最終的なデータ活用の目的が「お客様とのコミュニケーションを最適化することを通じて、長く自社サービスをご利用いただける関係を構築する」であれば、ロイヤルカスタマーと呼ばれる方がどのような経緯や目的でサービスをご利用いただいているのかを把握するために何らかの形で顧客構造を可視化することは必須となります。
この顧客構造可視化にあたり最も一般的に用いられるものに、「セグメントマップ(通称:セグマップ)」と「顧客KPIツリー」があります。いずれも、弊社がご支援させていただくプロジェクトでも頻繁に登場する手法です。このシリーズでは、「データドリブンな顧客マーケティングにおけるセグマップと顧客KPIツリーの役割と連携」と題して、計3回に分けてKPIツリーとセグマップについて解説しています。最終回となる今回は、セグマップと顧客KPIツリーの関連と適切な利用方法についてです。
本記事では、AIにディープリサーチさせた結果も引用しつつ、その違いと活用について解説していきたいと思います。
3. セグマップと顧客KPIツリーの関連と適切な利用方法
似たようで異なった目的をもつセグマップと顧客KPIツリーは、実際のマーケティング施策を考える上でどのように活用していくのが良いでしょうか?
AIは以下のように回答してくれました。
セグマップと顧客KPIツリーは、それぞれ異なる視点から顧客構造を捉えるものですが、相互に連携させることでより深い顧客理解と効果的なマーケティング活動に繋がります。
関連性:
- セグメントごとのKPI分析: セグマップで特定された各セグメントに対して、個別の顧客KPIツリーを作成・分析することで、セグメント特有の課題や機会を発見できます。例えば、優良顧客セグメントのリピート率を高めるためのKPIツリーと、新規顧客セグメントの初回購入後の継続率を高めるためのKPIツリーは異なる構造を持つ可能性があります。
- KPIツリーのセグメント別比較: 全体顧客のKPIツリーだけでなく、各セグメントのKPIツリーを比較することで、セグメント間の行動の違いや特性をより明確に把握できます。これにより、セグメントに合わせたよりパーソナライズされた施策展開が可能になります。
- セグメントの変化をKPIで追跡: マーケティング施策の実施によって、セグメントの構成比率や各セグメントのKPIがどのように変化したかを追跡することで、施策の効果をセグメントレベルで評価できます。
適切な利用方法(具体的な利用シナリオ例):
- 現状分析: まず、RFM分析などを用いて顧客をセグメントに分類し、各セグメントの規模や特徴を把握します(セグマップ)。
- 課題特定: 次に、各セグメントの顧客行動をKPIツリーで分解し、現状のKPI達成状況やボトルネックとなっているKPIを特定します。例えば、「優良顧客セグメントの平均購入単価が伸び悩んでいる」「新規顧客セグメントの初回購入後の離脱率が高い」といった課題が見つかるかもしれません。
- 施策立案: 特定された課題に対して、各セグメントに最適化されたマーケティング施策を立案します。例えば、優良顧客セグメントに対しては、高単価商品の提案や特別な優待プログラムを提供し、新規顧客セグメントに対しては、オンボーディングコンテンツの充実や初回購入者限定の特典を提供するといった施策が考えられます。
- 効果測定: 施策実施後、各セグメントのKPIがどのように変化したかをKPIツリーを用いて測定します。例えば、優良顧客セグメントの平均購入単価が向上したか、新規顧客セグメントの初回購入後の離脱率が低下したかなどを確認します。
改善: 効果測定の結果に基づいて、施策の改善や新たな施策の検討を行います。例えば、期待した効果が得られなかった場合は、KPIツリーのより深い階層を分析し、原因を特定して施策を修正します。
施策のPDCAにはなんらかの意味のある考察を繰り返す必要があり、データの裏付けも得ながら、社内のマネジメントの理解も得つつ次のステップに進んでいくには、多くの関係者のリソースと時間を要します。
従って、マーケターに許されている時間的制約の中で実施できるトライアル施策の数には限界があり、その中でできるだけ短時間で多くの成果を出す必要があり、AIが回答したような、すべての考えうるセグメントに対して個別にKPIツリーを作って比較検証する、といったことは理想像かもしれませんが、やや現実的ではないのではないかと考えられます。
実際、弊社がお手伝いするプロジェクトでは、基本的には顧客軸で見たKPIツリーは一つであることが大半であり、ただし、その中で全顧客を網羅的に捉えられるよう、新規顧客からリピート顧客まで包含していくような設計を行います。
その上で、時系列で見たときに各KPIがどのように推移しているのかを把握し、もっとも売上インパクトの高いと考えられるKPIから改善施策を実行していきますが、予めプロジェクトの初期段階でセグマップを確認し、注力して伸ばしていきたい顧客セグメントを決めておければ、KPIツリーの中でも特にどのKPIの改善に注力するべきか、の視点が変わってくることが想定されます。
例えば、売上=顧客数 x 顧客単価ですが、顧客数に注力するのか、単価の向上に注力するか、といったどこに重点をおくべきかの判断は、セグマップを俯瞰的に眺めることでより鮮明になることもあるでしょう。
実際にどのような観点でセグマップやKPIツリーを設計するべきか、についてはプロジェクト毎に細かく異なる部分がありますが、俯瞰的に状況を確認するのがセグマップ、施策を実行するための要素を可視化するのがKPIツリー、このように捉えておけば大きくは間違えないかと思われます。ぜひ上手に活用していきましょう。
本記事の内容についてご指摘やご不明の点、ご相談がありましたら是非お気軽にお問い合わせください。
