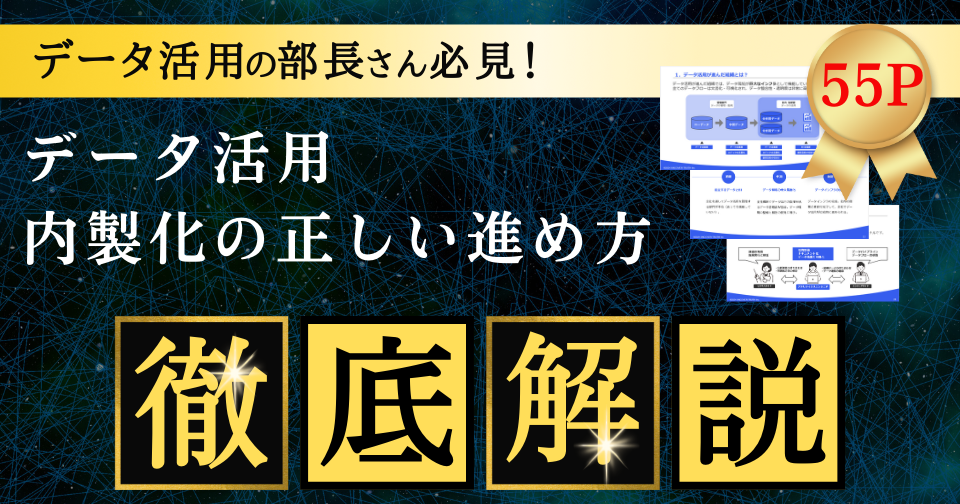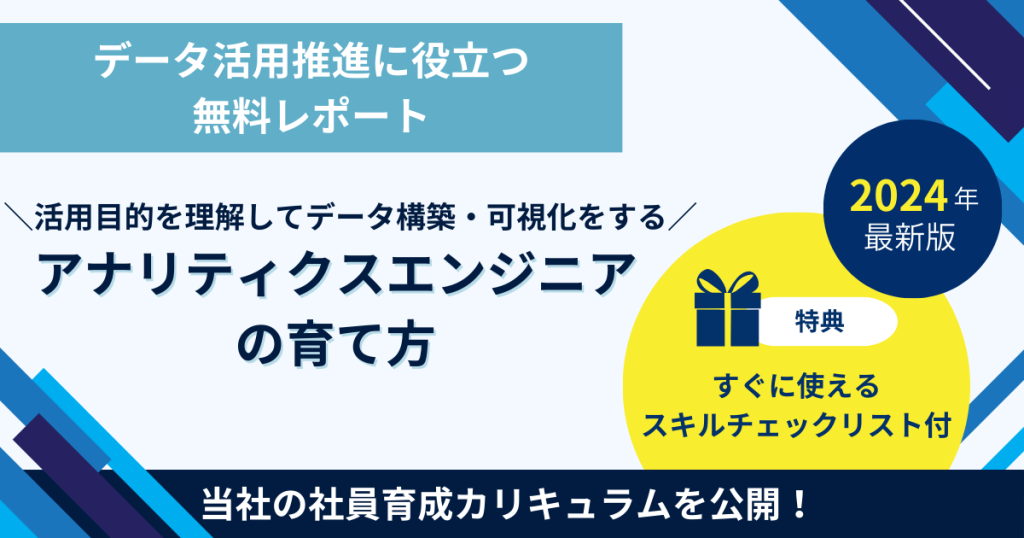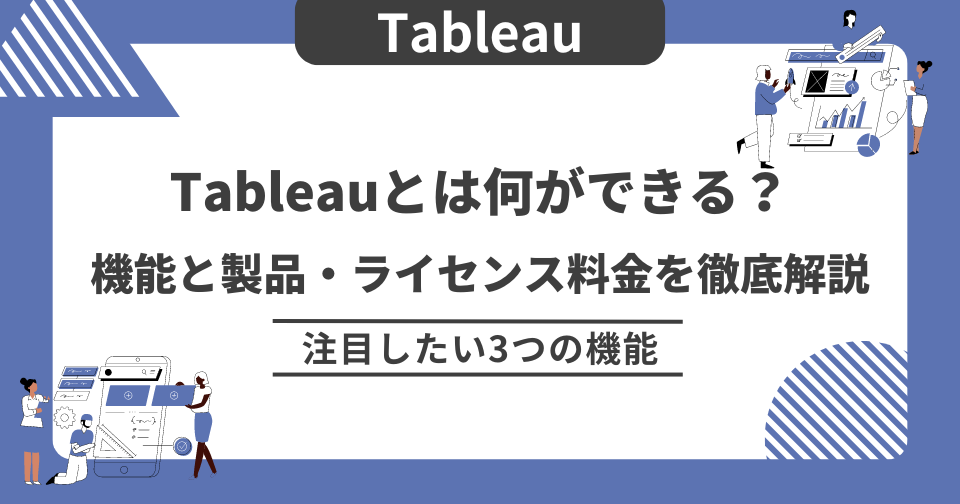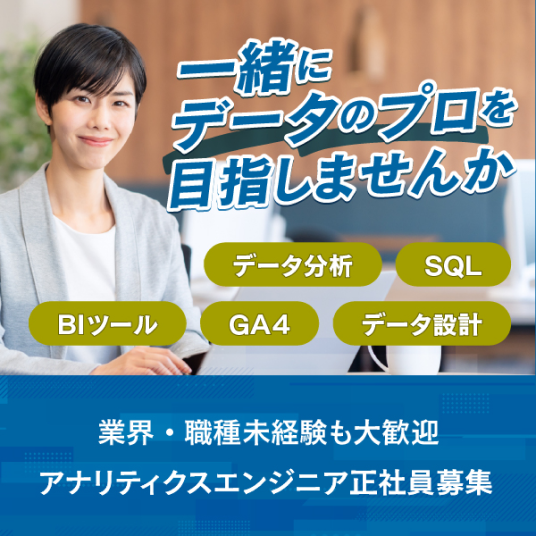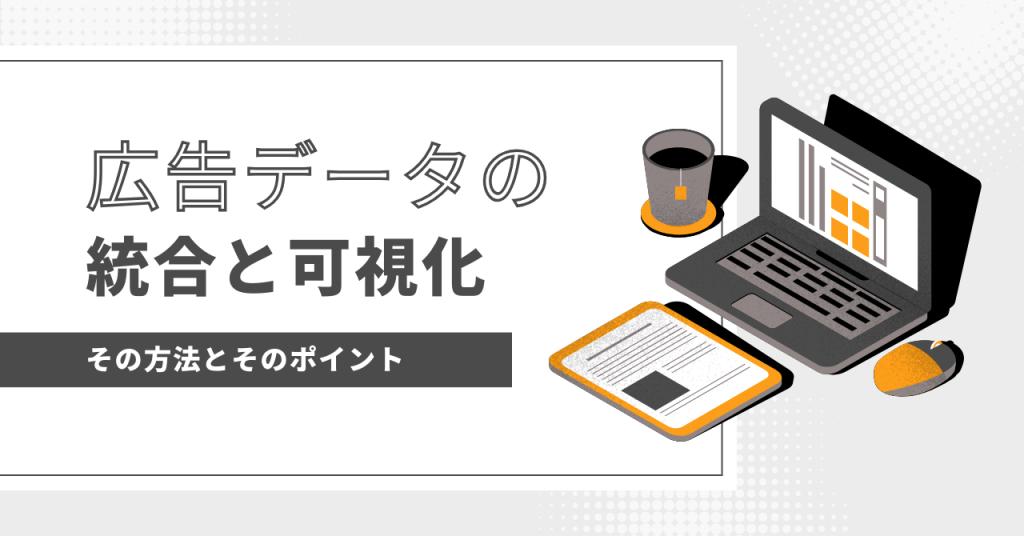目次
この記事が解決できること
- データファブリックが提供する3つの機能と業界別での活用事例がわかる
- データファブリックとデータメッシュ・データレイクそれぞれの違いがわかる
- 国内での導入事例をもつデータファブリック製品を知ることができる
はじめに
「データファブリックって聞いたことあるけど、結局どういうもの?」と感じていませんか?データ管理がますます複雑になる中で、企業のDX推進を支える新しいアプローチとして注目されているのがデータファブリックです。
この記事では、データファブリックの基本からデータメッシュやデータレイクとの違い、さらに具体的な活用事例や製品の比較までわかりやすく解説します。
データファブリックとは
データファブリックとは、企業内外に散らばったさまざまなデータを、場所や形式に関係なく統合・管理・活用できるようにするための新しいアーキテクチャです。従来のようにデータをひとつの場所に集めるのではなく、分散されたままでも、まるで1つの統一されたシステムのように扱えるのが特徴です。
この特徴は、必要なデータにすばやく安全にアクセスし、業務・分析に役立てることを可能にします。DXやデータに基づく経営を進める企業にとって、重要な基盤となりつつあるのがデータファブリックなのです。
データファブリックへの関心が高まる背景
データファブリックへの関心が高まる背景にあるのは、データの急速な増加と分散です。クラウドサービスやIoT・リモートワークの普及により、企業のデータは部署やシステムごとにバラバラに存在し、それを一元的に活用することが難しくなっています。
従来のような集中型のデータ管理では対応しきれず、さらにリアルタイムでの意思決定や柔軟なデータ活用が求められる今、より効率的で現場の変化に適応しやすい統合基盤の必要性が高まっています。このような背景から、データをつなぎ、全体を見える化できるデータファブリックに大きな期待が寄せられているのです。
データファブリックが提供する3つの機能
複雑なデータ環境でも、シンプルに扱える仕組みを提供する点は、データファブリックの大きな強みです。以下の表では、データファブリックの強みを支える、特徴的な3つの機能についてまとめています。
| 機能名 | 概要 | 効果・メリット |
|---|---|---|
| データ統合 | 異なる場所や形式のデータを一元的に接続・連携する機能 | サイロ化の解消、データをまとめて扱えることで分析や業務効率が向上。 |
| リアルタイムアクセス | 必要なデータへ即時にアクセスし、最新の情報を利用可能にする機能 | 判断や対応のスピードアップ、業務のリアルタイム化を実現。 |
| 自動化とガバナンス | データの整合性やセキュリティ、アクセス制御などを自動的に管理・運用する機能 | 人的ミスの削減、セキュリティの強化、コンプライアンス遵守の徹底。 |
データファブリックを使うと何ができる?
データファブリックを導入することで、企業は分散したデータをスムーズにつなぎ合わせ、1つのデータ基盤のように扱えるようになります。これにより、複数部門にまたがる情報を統合してリアルタイムで共有できるので、部門間の連携や迅速な意思決定が可能になります。
また、データの取得や整理・ルールの適用が自動化されることで、担当者の手間を減らし、運用コストを抑える効果も期待できるでしょう。さらに、データの整合性やセキュリティも強化されるため、安心して高度なデータ活用が行える環境を整えられます。
データファブリックとデータメッシュの違い
データファブリックとデータメッシュは、どちらも分散したデータの活用を目指していますが、考え方に違いがあります。データファブリックは全体を1つの仕組みでつなぎ、データを統合・自動化することに重点を置いています。
一方で、データメッシュは「それぞれの部門が自律的にデータを管理・提供する」ことを重視する考え方です。全体を1つの仕組みでつなぐのではなく、各部門が責任を持ってデータを扱う“分散型”です。
導入時の判断基準
データファブリックとデータメッシュのどちらを導入すべきかを判断するには、上記でも少し触れている通り、組織のデータ活用体制と目的を明確にすることが重要です。例えば、全社で統一されたデータガバナンスを重視し、IT部門が中心となって管理したい場合はデータファブリックが適しています。
一方で、各部門が自律的にデータを管理・活用し、組織のスピードと柔軟性を重視する場合はデータメッシュが効果的です。既存のITインフラやスキルセット・予算規模も判断材料になるので、導入前に目的と環境を整理したうえで、自社に合ったアーキテクチャを選びましょう。
データファブリックとデータレイクの違い
どちらも大量のデータを扱う基盤となるデータファブリックとデータレイクですが、役割や構造は明確に異なります。データレイクは、さまざまな形式のデータをひとつの場所に大量に蓄積する倉庫のような存在です。
一方、データファブリックはデータの保存場所に依存せず、分散されたデータを仮想的に接続して活用できるようにする仕組みです。つまり、データレイクは「ためる」、データファブリックは「つなぐ」に特化しており、用途によって使い分けることで、より高度なデータ活用が可能になります。
補完関係を活かす使い分け方
データファブリックとデータレイクは対立する概念ではなく、むしろ相互補完的に活用することで、より柔軟で強力なデータ基盤を構築できます。具体的には、データレイクを構造化されていないログデータや画像・動画などを大量に保管しておく場所として活用し、データファブリックはその中から必要な情報を、リアルタイムで抽出・統合・活用するといった使い方が考えられるでしょう。
この使い方からもわかるように、データレイクはデータの倉庫として、ファブリックがその倉庫をつなぐネットワークとしてそれぞれ機能します。両者の特徴を理解し、目的に応じて組み合わせることが、より高度なデータ活用を実現するポイントです。
データファブリックの活用事例
データ活用の課題を解決するため、データファブリックはさまざまな業界で導入が進んでいます。ここでは、金融・製造・医療の3つの業界に注目し、どのように活用されているのか事例を紹介します。
| 業界 | 活用内容 |
|---|---|
| 金融業界 | 複数の支店やチャネルに分散していた顧客データをリアルタイムで統合し、顧客のライフイベントや取引履歴に基づいた最適な商品提案を自動化。不審な取引の即時検知・対応も可能に。 |
| 製造業界 | 工場のセンサーから収集した稼働データや、サプライチェーン上の物流情報を統合・可視化。異常検知による予防保全や、生産計画に基づく在庫調整の自動化を実現。 |
| 医療業界 | 患者の電子カルテ・検査データ・服薬履歴などを統合して一元的に把握できる体制を整備。チーム間での情報共有を効率化し、患者ごとに最適な診療計画立案が可能に。 |
導入前後で何が変わるのか
データファブリックの導入前後では、情報の扱い方や業務プロセスに大きな変化が生じます。導入前は、情報を集約・分析に多くの時間と手間がかかり、リアルタイム性にも欠けていることから、意思決定の遅れにつながることも少なくありません。
しかし導入後は、分散したデータを一元的に把握できるようになるため、必要な情報はすぐに活用可能です。そのため、分析業務の効率化・顧客対応の迅速化・さらには新規ビジネスの立ち上げにもつながるなど、企業全体のデータ活用力の向上が期待できるでしょう。
データファブリック製品の比較
企業がデータファブリックを導入する際、日本国内での導入実績を持つ製品であれば、サポート体制や運用ノウハウが豊富で、実務に直結させやすいというメリットがあります。以下の表では、国内での導入事例が公開されている3つの製品を取り上げ、それぞれの特長と強みを比較していますので、ぜひ参考にしてください。
| 製品名 | 特長・強み |
|---|---|
| Talend Data Fabric | 豊富なデータコネクター(1,000以上)を持ち、高度なデータ統合・クレンジング・ガバナンス対応が可能。柔軟性が高く、複雑な環境でも適応しやすい。 |
| Microsoft Fabric | Power BIやAzureとの親和性が高く、使いやすさに優れる。生成AIとの連携で、直感的なデータ活用・分析が可能。クラウド環境との統合もスムーズ。 |
| IBM Cloud Pak for Data | AI・機械学習機能と密接に連携し、データ収集・分析・運用を一貫してカバー。エンタープライズ向けに高いセキュリティと拡張性を提供。 |
選定ポイントと自社に合う選び方
データファブリック製品の選定には、自社の課題や運用体制に合った視点での比較が欠かせません。まず、接続したいデータソースが製品に対応しているか、リアルタイム処理の必要性があるか、といったところが確認しておきたいポイントです。
くわえて、セキュリティやデータガバナンス機能の充実度、社内のITスキルに応じた導入・運用負荷の軽さも大切なポイントです。さらに、ベンダーのサポート体制やライセンス形態・将来的な拡張性も含めて総合的に判断し、自社のデータ戦略に最も適した製品を選びましょう。
まとめ
データファブリックは、複雑化・分散化する企業のデータ環境を統合し、より効率的で柔軟な活用を可能にする新たなアーキテクチャです。データメッシュやデータレイクとの違い・関係性を理解することで、自社に適したデータ基盤の方向性を見極めやすくなります。
また、業界ごとの活用事例や製品比較・選定のポイントを押さえておけば、導入後の成果をより高められるはずです。今後のデータ活用戦略において、データファブリックは重要な役割を担う可能性も秘めているので、今のうちにその全体像をつかんでおきましょう。
データ活用でお困りの方へ
私たちDX-Accelerator事業では、データ活用についての様々なスキルを持った人材が常駐でデータ活用支援を行うサービスを提供しています。
当事業はローンチから約3年(24年9月時点)ですが、これまでに様々な業界・業種のお客さまのお手伝いをさせていただいております。
少しでも興味を持ってくださったり、すでにご相談をしたいことがある方はお気軽にご相談ください。現在あなたの組織のフェーズがどこにあるかは関係ありません。まずはお話をしましょう。
もう少しサービスについて知りたい方はサービス紹介資料もご用意しています。