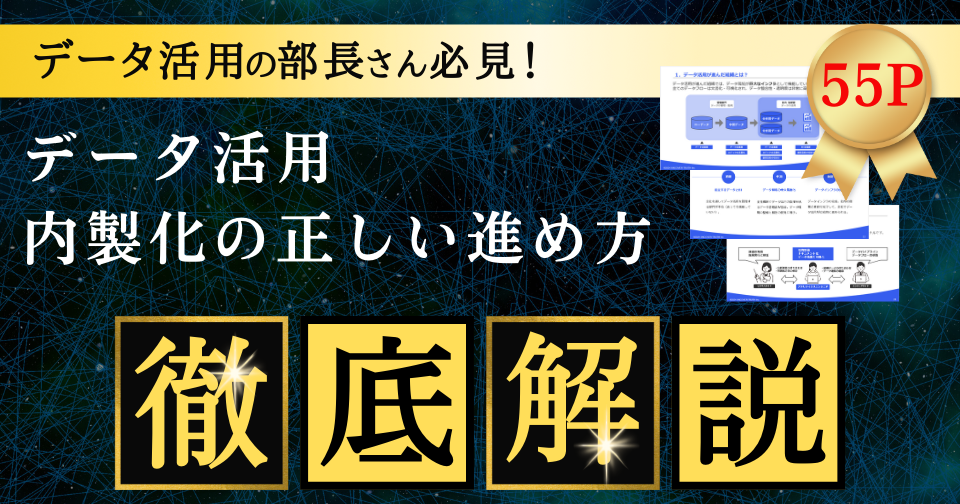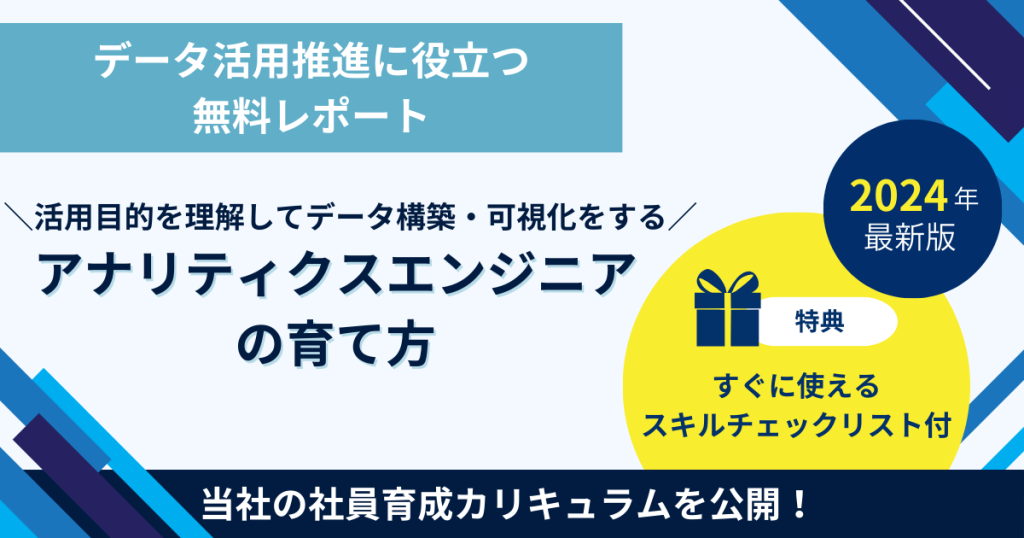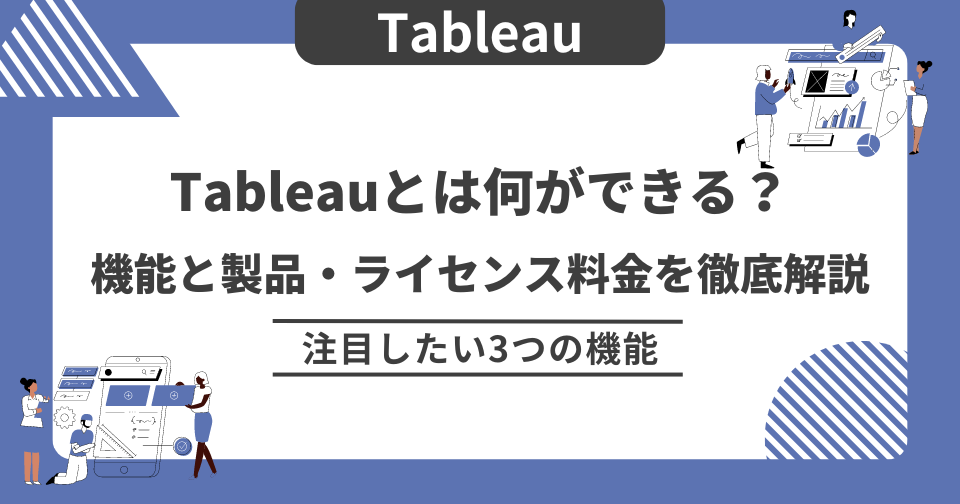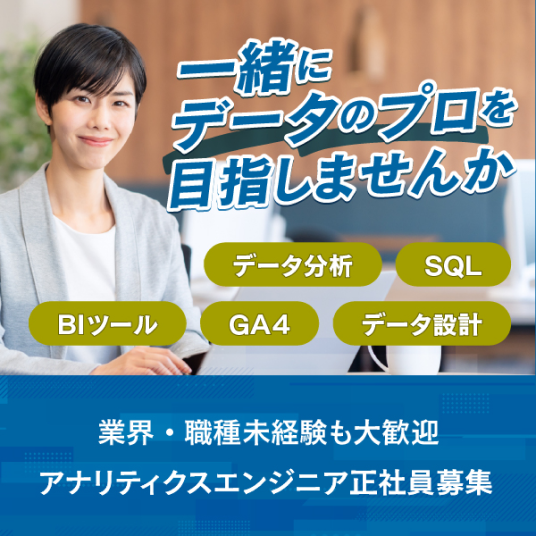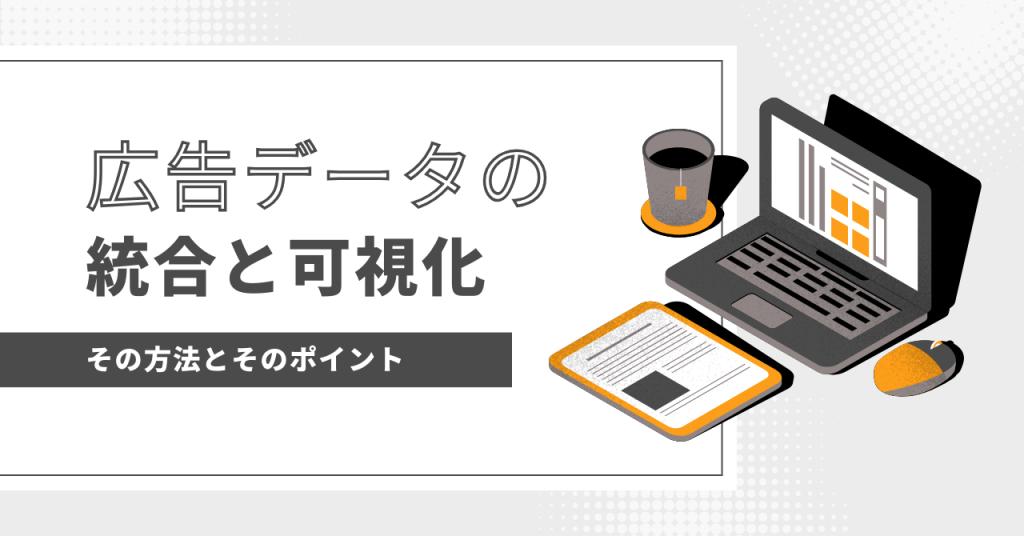目次
この記事が解決できること
- データメッシュの概要と従来型データアーキテクチャとの違いがわかる
- データメッシュの4つの原則を知ることができる
- データメッシュのメリットとデメリットがわかる
はじめに
ビジネスのあらゆる場面でデータの重要性が増す中、従来の一元的なデータ管理に限界を感じている方もいるのではないでしょうか。データメッシュは、こうした課題を解決するための新しい考え方です。
この記事では、データメッシュの基本的な仕組みや4つの原則、メリット・デメリット、さらにデータマネジメントの観点から見た運用のポイントにも触れながらわかりやすく解説していきます。
データメッシュとは?
データメッシュとは、これまでのように、すべてのデータを1つの部門が集中的に管理するのではなく、それぞれの部門が自分たちのデータを自ら管理・提供する分散型のアプローチを取る考え方です。例えば、営業部は営業に関するデータ、開発部は開発に関するデータを部門の責任で管理するというイメージです。
こうすることで、各部門がより早く、正確に必要なデータを扱えるようになり、全社的なデータ活用のスピードや精度が向上します。データメッシュは単なる技術ではなく、データの「持ち方」や「使い方」に関する組織全体の考え方を変える仕組みといえます。
従来型データアーキテクチャとの違い
データアーキテクチャとは、企業や組織がデータをどのように集め、保存し、管理・活用していくかを決める仕組みや考え方のことです。以下の表では、分散型のアプローチであるデータメッシュと、一元管理を行う従来型データアーキテクチャの違いをまとめました。
| 項目 | データメッシュ | 従来型データアーキテクチャ |
|---|---|---|
| 管理方法 | 分散管理型(各部門が自律的に管理) | 中央集約型(IT部門などが一元管理) |
| データの流れ | 各部門内で管理・共有 | 各部門 → 中央システム → 利用者 |
| 担当者 | 各ドメイン(部門)の担当者 | システム管理部門 |
| 代表的な技術 | セルフサービス基盤、API連携など | DWH、データレイクなど |
| 主な課題 | 組織文化やルール整備が必要 | サイロ化、反応の遅さ |
データメッシュの4つの原則
データメッシュは、2019年にZhamak Dehghani氏が提唱した考え方で、4つの原則に基づいています。この原則は、どのようにデータを扱い、管理し、共有すべきかという指針を示しており、組織文化や業務フローにも大きな影響を与える内容です。
ここからは、4つの原則について順に説明していきます。
- Domain ownership
- Data as a Product
- Self-serve data platform
- Federated computational governance
1.Domain ownership
Domain ownership(ドメインオーナーシップ)とは、データを使う部門やチームが、そのデータの責任も持つという原則です。これにより、現場の業務に詳しい人たちが、自分たちの判断でデータを活用・提供できるようになるので、全体のスピードや品質の向上が期待できます。
営業部門で考えてみると、顧客情報や売上データは営業部自身が管理し、品質や更新頻度を担保することで、他部門でも信頼して使える状態になります。IT部門だけに依存することなく、それぞれの部門が自律的にデータの管理者としての役割を担う点が特徴です。
2.Data as a Product
Data as a Product(データをプロダクトとして扱う)とは、データを製品のように考えるという原則です。この考え方の重要性は、データを記録や情報の集まりとしてではなく、価値を提供するものとして設計・提供する点にあります。
具体的には、検索しやすいファイル名の付与・定期的な更新・使用手順の整備といった工夫があげられます。こうした取り組みを行うことで、利用者は安心してデータを活用できるようになり、結果として、組織全体のデータ利活用を一段と進めることにつながるのです。
3.Self-serve data platform
Self-serve data platform(セルフサービス型データ基盤)は、誰でも簡単に必要なデータにアクセスし、活用できる環境を整えることを意味する原則です。この仕組みが大切な理由は、管理部門に依存せず、現場の担当者が自分で素早く分析や判断にデータを使えるようにするためです。
例えば、マーケティング部門でキャンペーンの効果をリアルタイムに分析したい場合、自分たちでデータを抽出・加工・可視化できるようになれば、意思決定は格段に早くなるでしょう。担当者自身の手で必要なデータにたどり着ける基盤は、全社的なデータ活用を促進するポイントのひとつです。
4.Federated computational governance
Federated computational governance(連合的ガバナンス)とは、全社共通のルールを保ちつつ、各部門が独立してデータ管理・運用できる仕組みを意味する原則です。ガバナンスを厳しくしすぎると現場の柔軟性が失われ、逆に自由すぎるとセキュリティや整合性が崩れてしまうため、この考え方が取り入れられています。
各部門が独自のデータ形式で運用していたとしても、データの命名規則やアクセス権限の考え方などを共通ルールで統一することで、全体として整った状態を維持できます。全体の秩序を保ちつつも、スピード感のあるデータ活用を実現するためには欠かせない原則といえるでしょう。
データメッシュのメリットとデメリット
データメッシュは、従来のデータ管理では解決しきれなかった課題に対応するための新しいアプローチですが、すべての組織にとって万能というわけではありません。導入によって得られるメリットもあれば、当然ながら乗り越えるべきデメリットも存在します。
ここでは、データメッシュを導入することで期待できる効果と、事前に理解しておきたい注意点について整理していきます。
データメッシュのメリット
データメッシュの大きなメリットは、各部門が自らのデータを管理・活用することで、意思決定のスピードと質が向上する点です。なぜなら、現場がデータの意味を最も理解しており、適切な判断材料をすぐに引き出せるようになるからです。
また、部門ごとに責任を持たせることで、データの品質向上や業務への意識改革も期待できるでしょう。これらの要素は組織全体のデータ活用力を底上げし、競争が激しい市場でのビジネス展開を支える基盤となるはずです。
データメッシュのデメリット
続いて、データメッシュのデメリットについて見ていきます。まずあげられるのは、各部門がデータの管理責任を負うため、専門知識やリソースが不足している場合は運用が難しくなる可能性がある点です。
くわえて、組織全体で統一されたルールや基準が整備されていないと、データの品質やセキュリティにバラつきが出てしまうリスクもあります。このように、データメッシュの導入と定着には、一定の準備と体制整備が必要であることを覚えておきましょう。
データマネジメントの観点から見るデータメッシュ
各部門がデータを管理するというデータメッシュの特性上、データの品質や一貫性をどう保つか、運用ルールやセキュリティをどう整備するかといった課題は避けられません。これらを適切にマネジメントできなければ、せっかくの分散型アプローチも混乱をまねく原因となってしまうからです。
本章では、データマネジメントの観点から、データメッシュにおける管理体制と運用上の基本的な考え方について解説していきます。
誰がデータを管理し品質を担保するのか
各部門がデータを管理するデータメッシュにおいては、データの更新や品質担保も部門が受け持ちます。そのため、部門内で「誰が責任を持って品質を担保するのか」を明確にすることが重要です。
そこで求められるのは、データプロダクトオーナーのような役割です。この担当者が、データの正確性や一貫性・更新頻度を管理することで、他部門から信頼される状態のデータを提供できるようになります。
運用ルールやセキュリティの整備
部門内での責任の明確化にくわえて欠かせないのが、全社として統一された運用ルールやセキュリティ対策の整備です。データメッシュのような分散型の運用では、ルールが曖昧なままだと部門ごとの運用にばらつきが生じ、データの信頼性や安全性が損なわれる恐れがあるからです。
したがって、データの命名規則やアクセス権限の設定基準、暗号化の方法など、全社共通で守るべきガイドラインはあらかじめ定めておきましょう。さらに、ログ管理や監査機能なども組み込むことで、不正利用や情報漏洩のリスクを抑えられます。
まとめ
データメッシュは、従来の一元管理とは大きく異なり、部門ごとにデータの責任を持つという新しいアプローチです。4つの原則に基づく運用により、柔軟でスピーディーなデータ活用が可能になります。
一方で、導入にはガバナンスやルール整備・担当者の明確化といった、いくつかの課題にも対応しなければなりません。データ活用を促進する技術としてだけではなく、組織文化や業務フローを見直すきっかけにもなりえるので、導入の候補として検討してみてはいかがでしょうか。
データ活用でお困りの方へ
私たちDX-Accelerator事業では、データ活用についての様々なスキルを持った人材が常駐でデータ活用支援を行うサービスを提供しています。
当事業はローンチから約3年(24年9月時点)ですが、これまでに様々な業界・業種のお客さまのお手伝いをさせていただいております。
少しでも興味を持ってくださったり、すでにご相談をしたいことがある方はお気軽にご相談ください。現在あなたの組織のフェーズがどこにあるかは関係ありません。まずはお話をしましょう。
もう少しサービスについて知りたい方はサービス紹介資料もご用意しています。