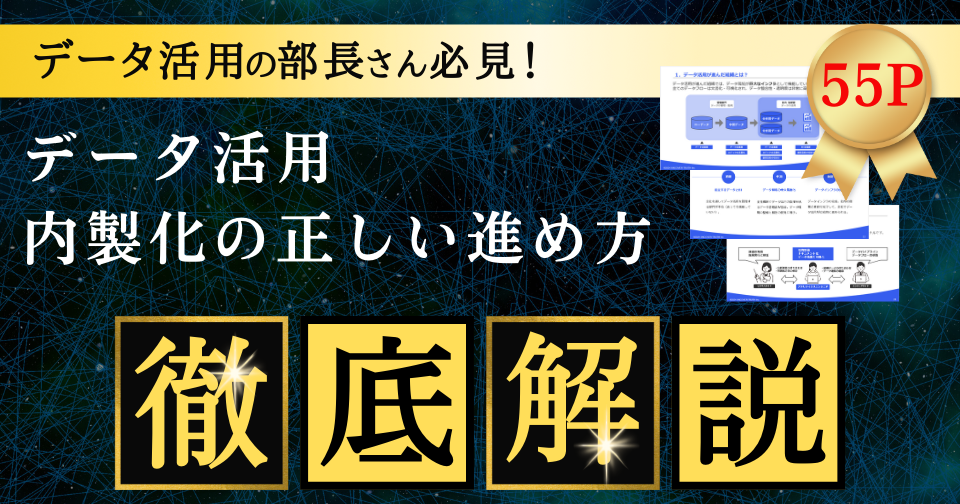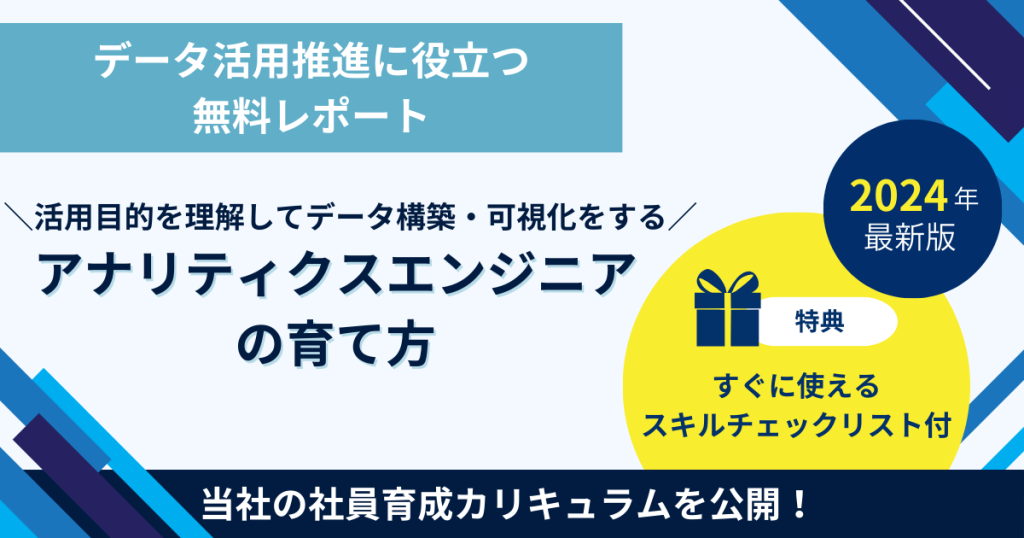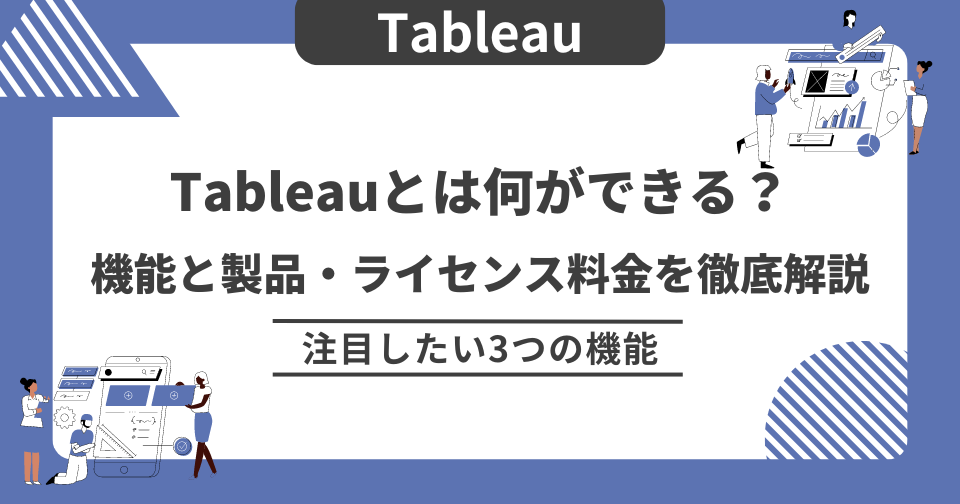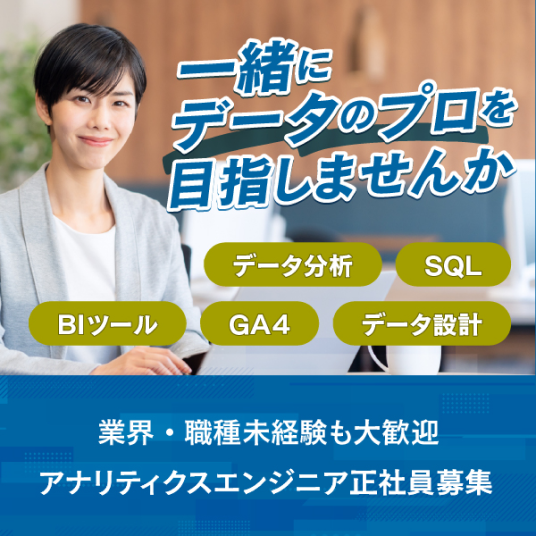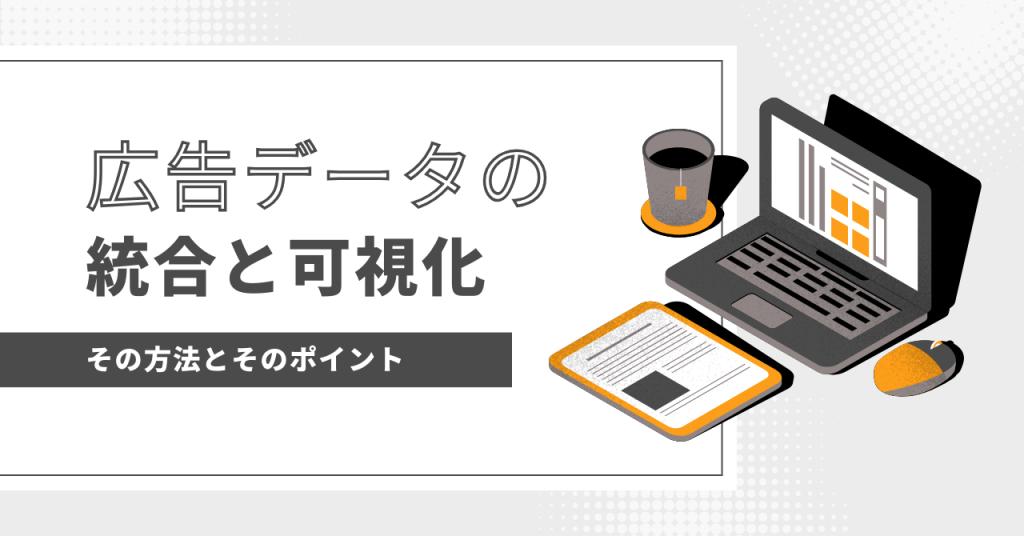目次
この記事が解決できること
- データレイクハウス・データレイク・データウェアハウスの違いがわかる
- データレイクハウスのメリットとデメリットがわかる
- 3つのデータレイクハウス製品について概要や特長を知ることができる
はじめに
ビッグデータの利活用が進む中、データウェアハウスやデータレイクでは対応しきれない課題も見られるようになってきています。そうした背景の中で注目を集めているのが、データレイクハウスという新しいデータ管理の仕組みです。
本記事では、データレイクハウスの基本からデータウェアハウスやデータレイクとの違い、さらに導入する際のメリット・デメリットをわかりやすく解説します。
データレイクハウスとは?
データレイクハウスとは、データレイクとデータウェアハウスの特徴を組み合わせた、新しいデータ管理の仕組みです。従来、非構造化データの保存にはデータレイク、構造化データの分析にはデータウェアハウスが使われてきましたが、この2つを併用するにはコストや管理面での課題がありました。
そこで登場したのがデータレイクハウスです。データレイクとデータウェアハウスの利点を併せ持つことから、コストを抑えつつ高性能なデータ活用環境を実現する基盤として、注目されている技術です。
データレイクとデータウェアハウスの違い
データレイクは、構造化・半構造化・非構造化といったあらゆる形式のデータをそのまま保存できる柔軟な仕組みで、保存コストが低く拡張性も高い点が特徴です。一方、データウェアハウスは、事前に定義されたルールに基づいて整備された構造化データを扱い、高速かつ正確な分析処理に優れています。
つまり、データレイクは「自由さ」、データウェアハウスは「整然さ」に強みがあります。データレイクハウスは、この2つの利点を融合し、柔軟性と分析性能の両立を可能にする新しいアプローチなのです。
データレイクハウス・データレイク・データウェアハウスを比較
ここでは、データレイクハウス・データレイク・データウェアハウスの異なる特性について下記の表にまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
| 特性 | データレイクハウス | データレイク | データウェアハウス |
|---|---|---|---|
| 対象データ形式 | 構造化~非構造化すべてに対応 | 構造化、半構造化、非構造化 | 主に構造化データ |
| 保存コスト | 中〜低コスト | 低コスト | 高コスト |
| スキーマ設計 | 両方に対応 | スキーマオンリード(後から定義) | スキーマオンライト(事前に定義) |
| リアルタイム分析 | 得意 | 苦手 | 得意 |
| 柔軟性 | 高い | 非常に高い | 低い |
| セキュリティ・ガバナンス | 製品によって整備されている | 弱い傾向がある | 強固 |
| 活用場面 | 多様なデータ分析と業務統合 | ローデータの保管・機械学習・実験用途など | 定型的なビジネス分析 |
データレイクハウスのメリット
企業が日々扱うデータはますます多様化し、その活用方法も高度化しています。そんな中、データレイクハウスは多様なデータ形式への柔軟な対応と、高度な分析処理を両立することで、企業のデータ活用の幅を大きく広げています。
ここからは、データレイクハウスが企業にもたらす具体的なメリットについて、2つの観点から見ていきましょう。
コスト効率と拡張性
データレイクハウスの大きなメリットのひとつは、コストを抑えつつ大規模なデータ処理が行える点です。安価なクラウドストレージを活用することで、従来のデータウェアハウスと比べて格段に低コストなデータ保存を実現しています。
また、クラウドベースのスケーラブルな構造により、必要に応じてリソースを拡大・縮小できる拡張性も魅力です。これにより、データ量の急増や分析ニーズの変化にもスムーズに対応できるため、中長期的に見ても無駄のないコスト運用が可能になります。
リアルタイム分析対応と柔軟性
リアルタイムでのデータ処理と分析に強い設計がなされているところも、データレイクハウスの強みです。データレイクハウスでは、データが保存されるとほぼ同時にクエリや分析が可能になるため、迅速な意思決定につなげることができます。
さらに、構造化・非構造化を問わず多様なデータ形式に対応しているので、システムや用途に応じて柔軟に活用方法を変えられます。このようなリアルタイム性と柔軟性の高さは、マーケティング施策や業務改善を加速させる重要な要素になるはずです。
データレイクハウスのデメリット
多くのメリットをもたらすデータレイクハウスですが、導入や運用にあたってはいくつかの注意点も存在します。従来とは異なる新しい構造を持つがゆえに、単純に置き換えるだけでは活用しきれない場合もあるため、メリットだけでなくデメリットについても把握しておくことが必要です。
ここからは、データレイクハウスのデメリットについて詳しく解説し、導入前に理解しておくべきポイントを明確にしていきます。
導入・運用の難しさ
データレイクハウスの導入には、一定の専門知識と経験が求められます。なぜなら、データレイクとデータウェアハウス、両者の特性を兼ね備えている分、設計や運用ルールの策定が難しいからです。
くわえて、既存のIT基盤との連携や移行作業にも時間とコストがかかるため、インフラや人材の整備が不十分な場合には運用コストやトラブルのリスクも高まります。そのため、導入・運用を成功させるには、社内の技術力だけでなく、外部ベンダーの支援を受ける体制づくりが重要です。
セキュリティ・ガバナンス面の課題
多様なデータを一元的に扱える自由度の高さが魅力のデータレイクハウスですが、セキュリティやデータガバナンスの観点では注意が必要です。非構造化データや大量のリアルタイムデータを取り扱う環境では、アクセス制御やデータの追跡管理が複雑になりやすく、適切な権限設定やログ管理を怠ると情報漏洩や不正利用のリスクが高まるからです。
したがって、データの整合性や品質を維持するルール作り、法令や業界基準に準拠したガバナンス体制の構築が欠かせません。これらの課題に対応するためには、ガバナンス体制を強化し、セキュリティポリシーを徹底させるといった、組織全体での取り組みが重要です。
データレイクハウス製品・サービス紹介
データレイクハウスは技術としての注目だけでなく、すでに多くの企業が製品・サービスとして提供を始めています。それぞれに強みや適した用途があり、導入を検討する際には、自社のニーズに最も合致する製品を見極めることが大切です。
本章では、注目したいデータレイクハウス製品・サービスを3つ取り上げ、概要や特長をわかりやすく紹介していきます。
- Databricks Lakehouse Platform
- Snowflake
- Amazon SageMaker Lakehouse
1.Databricks Lakehouse Platform
Databricks Lakehouse Platformは、データレイクとデータウェアハウスの機能を一体化したクラウドベースのプラットフォームです。Apache Sparkをベースに構築されており、高速なデータ処理と機械学習への対応力が強みです。
また、Delta Lakeという独自のストレージレイヤーを活用することで、ACIDトランザクションやバージョン管理を実現し、信頼性の高いデータ分析を可能にしています。機械学習やBIツールとの統合もスムーズで、データサイエンスから業務分析まで多様な用途に対応しています。
2.Snowflake
Snowflakeは、クラウドネイティブなデータプラットフォームとして広く利用されているサービスで、近年ではデータレイクハウス機能も強化されています。マルチクラウド対応であり、AWS(Amazon Web Services)・Microsoft Azure・GCP(Google Cloud Platform)といった主要なクラウド上で利用可能です。
Snowflakeの特徴は、セキュリティやガバナンスの強化・データ共有のしやすさ・そしてSQLベースのシンプルな操作性にあります。複雑なインフラ管理を必要とせず、ユーザーが迅速に分析や機械学習プロジェクトに着手できる環境が整っているので、幅広い業種・業界で活用されている製品です。
3.Amazon SageMaker Lakehouse
Amazon SageMaker Lakehouseは、AWSが提供する機械学習サービスSageMakerとデータレイク機能を組み合わせた統合プラットフォームです。S3を中心としたデータ保存と、RedshiftやAthenaなどの分析ツールを連携させることで、構造化・非構造化データをシームレスに扱える環境を提供しています。
なかでも、SageMaker上でのモデル作成やトレーニングに直接データレイクの情報を活用できる点が強みで、データサイエンティストにとって非常に効率的な開発環境となります。高度なデータ処理とAI活用を目指す企業にとって、Amazon SageMaker Lakehouseは効果的な選択肢のひとつです。
まとめ
データレイクハウスは、データレイクとデータウェアハウスの長所を取り入れた、新しいデータ管理の仕組みとして注目を集めています。柔軟性と拡張性に優れた構造を持ち、コストを抑えながらも高度な分析が可能な点は大きな魅力といえるでしょう。
一方で、導入や運用には専門的な知識と体制が必要となるため、メリットだけでなくデメリットもしっかりと理解しておくことが重要です。データに基づいた意思決定を実現したい企業にとって、データレイクハウスをどのように活用できるか、検討する価値は大いにあるのではないでしょうか。
データ活用でお困りの方へ
私たちDX-Accelerator事業では、データ活用についての様々なスキルを持った人材が常駐でデータ活用支援を行うサービスを提供しています。
当事業はローンチから約3年(24年9月時点)ですが、これまでに様々な業界・業種のお客さまのお手伝いをさせていただいております。
少しでも興味を持ってくださったり、すでにご相談をしたいことがある方はお気軽にご相談ください。現在あなたの組織のフェーズがどこにあるかは関係ありません。まずはお話をしましょう。
もう少しサービスについて知りたい方はサービス紹介資料もご用意しています。